ホームページ用画像と印刷用画像の違い
ホームページを運営していると、チラシやパンフレット等の印刷物をご依頼されることも多いと思います。
どちらも『画像を作成』するわけですが、ホームページ用の画像と印刷用の画像との違いを簡単に説明してみようと思います。
画像の大きさが違う
「ホームページ上の画像を印刷したらボヤけてた!」という経験はありませんか?
これは、ホームページ上で使用する画像については解像度(密度)が低く設定されているからなのです。
ホームページ用の画像では解像度(密度)が72dpiから96dpi程度で良いのに対し、印刷用は350dpiも必要になります。
※dpi → dot / inch(ドット パー インチ)つまり、1インチ当たりどれだけの点があるか?ということです。
同じ大きさの枠に対して点がたくさんある(密度が高い)方が『きめ細かい画像』というわけです。
ホームページは『画面(モニタ)』で見ますよね?
画面(モニタ)では1インチ当たりの密度が低いので、これ以上細かい画像は必要ない(それ以上キレイに表示されない)ですし、あまり大きな画像ファイル(きめ細かい画像)にしてしまうと画像自体のデータサイズが大きくなり、結果ホームページの表示が遅くなってしまいます。
なので、なるべくデータサイズの小さな画像で作ってあります。
例えば横幅10㎝の画像を作るとして
ホームページ用だと横幅 378pxで作成すればよいのに対し、
印刷用だと横幅 1378pxが必要になります。
約3倍~4倍になっちゃいますね。
印刷用の画像をパソコンのモニタ(画面)で見ると大きく見えてしまうのは、このせいです。
もちろん画像を作る際にも、印刷用だと細かい部分もきっちりと作り込まないとボヤけたりズレたりしてしまいますし、大きさも大きいぶん手間も時間もかかるわけです。
色の作り方が違う
画面(モニタ)上では『RGB』という色の形式で表示されます。
R—Red
G—Green
B—Blue
画面(モニタ)は『光』で色を表現しますよね?
そう、光の三原色です。
赤・緑・青の色を組み合わせて様々な色を作り出しているのです。
話題はそれますが、先日話題になった青色LEDはこの意味で「LEDで全ての色を表現できるようになった」という革命を起こすものでした。
では印刷ではどうやって色を作るのでしょう?
印刷用では『CMYK』という色の形式が使われます。
C—Cyan
M—Magenta
Y—Yellow
K—Black
これらの色(水色・ピンク・黄色・黒)のインクを組み合わせて様々な色を作り出します。
実はRGBの方が表現できる色が多いため、RGBで作成した色を印刷用にするとどうしてもくすんだり違う色になったりしてしまいます。
ですので印刷用の画像データは『CMYK』で作成します。
最後に
どうしてこういうことを書こうと思ったかというと、
「印刷用データの単価が高いのは何故?」と聞かれたことがあるからです。
上記の通り、ホームページ用と印刷用とでは『手間(必要な時間)』がかなり違います。
そういった『手間賃(時間給)』と『使用ソフトウェアの経費』も入るため、印刷用データの作成単価は高くなってしまうわけです。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
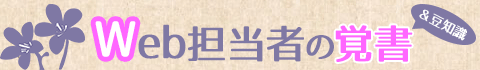
コメントを書く